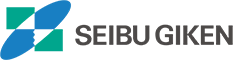2023年4月に完成した種子島宇宙センターの
第3衛星フェアリング組立棟(SFA3)。
組立棟の中で人工衛星が納まるフェアリング内部の空調を維持する
除湿機が、西部技研のデシカント除湿機『ドライセーブ』だ。
SFA3建設プロジェクトの起ち上げから携わるJAXA施設部の
田嶋氏を訪ね、宇宙・ロケット事業における除湿機の重要性と、
『ドライセーブ』を採用した理由、未来への可能性を語っていただいた。
第3衛星フェアリング組立棟(SFA3)。
組立棟の中で人工衛星が納まるフェアリング内部の空調を維持する
除湿機が、西部技研のデシカント除湿機『ドライセーブ』だ。
SFA3建設プロジェクトの起ち上げから携わるJAXA施設部の
田嶋氏を訪ね、宇宙・ロケット事業における除湿機の重要性と、
『ドライセーブ』を採用した理由、未来への可能性を語っていただいた。

-
JAXA 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
施設部 射場施設課 課長
田嶋 一之氏 Tajima Kazuyuki(写真左) -
株式会社 西部技研
プロダクト営業本部 国内営業部 東日本営業課
大場 夏樹 Oba Natsuki(写真中央) -
株式会社 西部技研
プロダクト・マネジメント本部 営業技術課 マネージャー
藤元 幸司 Fujimoto Koji(写真右)
TOPIC
国民の熱い期待が集まる
ロケット事業。
打ち上げ成功は
「達成よりも安堵感」。
- 大場
- H2Aロケット打ち上げ成功おめでとうございます(2025年6月29日 H2Aロケット50号機打ち上げ)。ライブ配信を拝見しました。一端に携わっている企業の人間として、通常とは別軸の誇らしさを感じました。
- 田嶋氏
- ありがとうございます。ひとまずホッとしました。1カ月前から緊張感の中にいましたから、今は責任の重圧から解放され、安堵感の方が大きいですね。
- 藤元
- ホッとする気持ち、よく分かります。打ち上げの瞬間は「おぉ~っ!!」と思うんですよ。ただ、技術者としてはどうしても失敗した場合を想定するから、つい身構えてしまいます。どうやって実証をしていくのだろう…と他人事ではなくて。
- 田嶋氏
- ええ、かつてH3ロケットの打ち上げが失敗した時は実証も大変で、当分打ち上げは無理じゃないかという危機感すらありました。最近は国民から多くの応援をいただけているので、本当にありがたい。国民の中にも、ロケットの打ち上げを技術的に受け継いでいこうという気持ちが広がっているのだと実感しています。


MISSION│episode 1
フェアリング内の温湿度を
『ドライセーブ』で管理。
衛星を守り、
宇宙まで無事に運び届ける。
- 大場
- 西部技研のデシカント除湿機『ドライセーブ』は種子島宇宙センターの第3衛星フェアリング組立棟(SFA3)に設置されています。あらためて、『ドライセーブ』はどのような役割を担っているのでしょうか。
- 田嶋氏
- ロケットの先端にあるフェアリングは、衛星を保護するカバーです。フェアリングの内部は打ち上げの瞬間まで、衛星ユーザーが要求する温度や湿度を維持しなくてはなりません。『ドライセーブ』の役割は、組立棟から射場に移動する専用車に乗せる直前までの、フェアリング内の温湿度をはじめとする空調の管理。そして、海外の衛星ユーザーに開示するための保管状況のデータ記録です。
- 大場
- 打ち上げの瞬間に注目が集まるロケット事業ですが、じつはその前後にも重要なミッションがあるのですね。
- 田嶋氏
- ええ。衛星はお客様からの大切な預かりもの。いわばプレゼントです。私たちはこの精密なプレゼントを、宇宙まで無事に運び届けなければなりません。フェアリング内部の温湿度が上がると、レンズの誤作動やセンサーに影響を及ぼすカビの発生など、衛星の精密機器に不具合が生じる恐れがあります。衛星本体の性能を担保しきれないとなると、国としての責任問題。温湿度条件を逸脱しないということは、衛星を守り、国の信頼を守るということです。
- 藤元
- 確かに。衛星が宇宙の軌道に乗って、衛星に搭載されたサービスが無事に始まる──。その瞬間を見届けるまでが弊社の除湿機と我々のミッションですね。
MISSION│episode 2
4℃の冷水が回る中、
露点0℃を達成せよ。
衛星ユーザーの
特殊な要求をクリア。
- 大場
- 弊社は2011年頃からJAXA様とお取引をいただき、種子島宇宙センターや筑波宇宙センターに標準品を納品していました。ただ、今回のSFA3プロジェクトに関してはご紹介ではなく、純粋に製品の性能を見込んでくださってのご依頼だったそうですね。
- 田嶋氏
- ええ。SFA3プロジェクトはとても特殊で、海外の衛星ユーザーからフェアリング内の露点0℃以下で吹いてくれという要望があり、急遽除湿機能を見直す必要がありました。しかも、チラーで4~9℃の冷水を回すというこちらの条件をクリアした上で、露点0℃を達成しなければならない。打ち上げの3カ月ほど前、ちょうどコロナ禍の真っ只中のことです。外出もままならない時期、

- 大場
- 企業や製品を探す上でどのような基準をお持ちだったのでしょうか。
- 田嶋氏
- JAXAの条件をクリアできるかどうか、という点に尽きます。空調機の場合、衛星ユーザーからの温湿度の要求を確実に担保してください、というのが私たちの依頼です。稼働期間は2週間程度。フェアリングで衛星をカバーして、組立棟から射場へ出ていくまでの短い期間ではありますが、衛星を守る上では重要な期間です。
MISSION│episode 3
『ドライセーブ』で
チラーの有効利用が可能に。
コストを抑えつつ
安定した空調力を発揮。
- 藤元
- 『ドライセーブ』のどのような点に注目なさいましたか。
- 田嶋氏
- 『ドライセーブ』は空気中の水分を吸着して除湿しますよね。これまで通り4℃の冷水を使っても確実に除湿ができる、非常に良いシステムだと感じました。通常の空調機だとコイルで空気を冷やすだけ。それでは4℃の水を使うフェアリング内で露点0℃は難しい。マイナス温度の冷水を供給し湿度を緩和することもできますが、特殊な冷水能力を持つチラーを選び直す必要があり、膨大な費用がかかってしまいます。
- 藤元
- 確かに。『ドライセーブ』は、デシカント除湿ローター技術による低露点での安定した吹き出しがひとつの強み。心臓部である活性シリカのハニカムローターは1984年に弊社が世界で初めて開発し、商品化したもので、今回搭載したものは更に改良されたものですから、高く評価していただきありがたいです。
- 田嶋氏
- 『ドライセーブ』で現状のチラーを有効利用できたし、これまでのフェアリング空調よりも安定性があります。技術者の皆さんの技術も長けていて、非常にコンパクトに納めていただきました。JAXAは国の機関なので、要求を満たせる機械であるなら安価な方がいいんです。ですから、基本的に僕らが発注する工事の図面には機械の性能だけを記し、メーカー名は表記しません。ただし、今回のSFA3の空調については特殊ですので、西部技研さんの社名を表記したと記憶しています。建物一式の総費用が約75億という大規模工事の中、1社だけ業者を指定するのは異例中の異例でしたが、ユーザー側の特殊な要求を確実に満たす機械でしたから、書いて残す必要があると判断しました。大規模で特殊なプロジェクトだからこそ、特殊な製品と出会えたという手応えがあります。

CONNECT│episode 1
打合せを通して生まれた
技術者同士の絆。
経験と実績が活きた
スピーディな仕事。
- 大場
- ご依頼当時に対応した2名の技術者は、大のロケット愛好家。かなり前のめりになって設計に取り組んでいました。憧れていたロケット関連のプロジェクトに仕事で携われるなんて貴重な経験です。
- 田嶋氏
- 当時、除湿機探しは非常に難航していまして、西部技研さんにたどり着くまで2カ月ほどかかりました。連絡を取りすぐに打合せをしたのですが、資料を見た技術の方は「あ、いけますね、これ」と即答。モード別のボタンを押した時の機械の動きや、データの吸出し方法など、かなり細かい要求にもすべていい対応をいただき、頼もしかったですね。技術者同士だから話が早く、1週間後に図面が上がってきたのにも驚きました。
- 藤元
- 西部技研はカスタムオーダーが基本。お客様の細かい要望に応えてカスタマイズした機械を設計・製造するのを最も得意としています。ですから早いスピードで設計し、お客様が望む仕様をご提供できたのでしょう。オーダーが細かくなるほど、技術者同士で話をした方が早いし、私たちもお客様のご要望が明確な方が助かります。
- 大場
- 様々な案件で培ってきたノウハウも弊社の強み。ご要求事項が厳しいお客様も多く、数多の難関をクリアしてきた経験が、今回のプロジェクトでも活かせたんだと思います。
CONNECT│episode 2
種子島に近い福岡が
西部技研の基幹。
想定外のアクシデントにも
迅速に対応。


- 田嶋氏
- 確か2022年でしたか、試験中に圧力の関係で発熱が上がり過ぎて、温湿度が要求未達になった時がありました。原因はこちらの圧力で『ドライセーブ』に非はなかったのですが、次の打ち上げ予定日が迫る中、すぐに技術者の方が種子島に来て除湿面を調整してくださり、非常に助かりました。本社が福岡で、メンテナンスしやすい場所に部署があるのも私たちにとって心強い要素です。
- 大場
- 西部技研はサービス拠点が全国にあり、関係企業との協力体制も構築しています。種子島宇宙センターは弊社の本社(福岡県古賀市)から比較的近く、総合的に見ていい結果につながりました。そう思うと感慨深いですね。
- 田嶋氏
- 『ドライセーブ』は他の部署にも紹介しましたし、実際に引き合いもありましたよね。今後も依頼は増えると思います。技術的に多くの企業に参入いただくことは、宇宙業界の悲願。新しいメーカーさんの参入で価格競争が生まれ、技術力も上がっていく、私たちにとってもありがたい話ですし、海外に追いつく力になります。日本の打ち上げは成功率が高い反面、回数的にはまだまだ多いとは言えません。多数打っていくのであれば、技術を展開して共有し、コストを下げないと。衛星ユーザーさんに選んでいただくためにも重要な課題です。
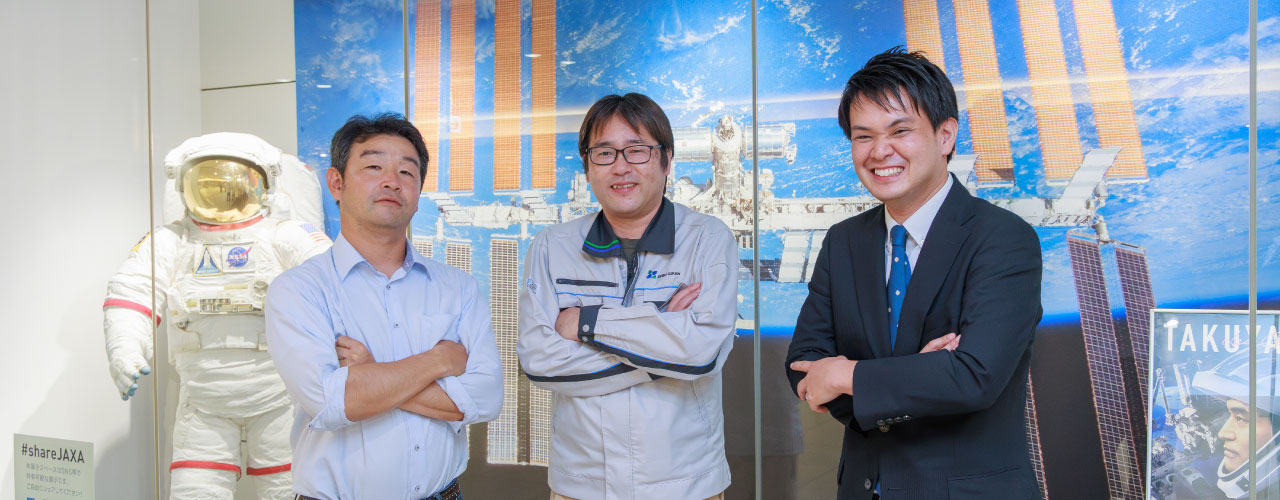
FUTURE│episode 1
10年に1度の大プロジェクト
の経験を未来へ。
得たものは記録し、
次世代につなぐ。
- 田嶋氏
- 造るものが特殊だからこそ、日頃から色々なメーカーさんと話すべきだと感じています。今後、衛星の温湿度条件は緩和していくのか、より厳しくなるのか──10年後、20年後を見据えてメーカーさんと話すことが私たちの使命。組立棟の建設は10年とか15年に1度の大プロジェクトなので、私が得たものは文面に残し、次の世代とまたタッグを組んで作業する。そういう縁も大事にしたいんです。
- 大場
- 私自身も当時の担当から業務を引き継ぎ、前任者が残した資料や仕事に向き合う姿勢を知りました。当時の苦労や対応を理解して、今があります。異動はあっても残すべきもの、伝えるべきものがある点では同じですね。
- 藤元
- どのプロジェクトにもストーリーがあります。ロケット事業のストーリーは起承転結の「結」がきちんと打ち上がって終わるというイメージ。「結」に至るまでのエピソードにも困難と喜びがあり、特に印象に残ります。そういったドラマを各支店で語り継ぎ、企業全体で共有できるのもひとつの財産でしょう。
- 田嶋氏
- 嬉しいですね。現場サイドか発注している側か、どちらかが持っている情報があれば必ず次につながります。というのも、SFA3の建設はSFA2を建てた設計事務所やメーカーに当時の話を聞くところから始めたからです。人として技術として「残し、伝える」必要性を強く感じました。そのためにも、大手一社に丸投げではなく、色々な企業にアッセンブルして造っていく方が絶対に面白いなと思っています。
- 藤元
- 技術者は一匹狼タイプか、コラボ好きなタイプ。私はどちらかというとコラボ好きなので、色々な人と話をして仕事をする面白さには共感します。
FUTURE│episode 2
「独創と融合」。
技術と提案力で
厳しい要求をクリアし
宇宙に還元を。
- 田嶋氏
- 西部技研さんはパッケージ品を売るだけではなく、提案力のある企業。そこに面白みがある。今回のように特殊な要求に応えられる技術と提案力があるのは珍しいですよ。
- 大場
- 勇気づけられます。今後のJAXA様からのご相談にもご期待以上の提案をしないと。身が引き締まる思いです。
- 藤元
- 西部技研の経営理念は「独創と融合」です。お客様から「こういうもの作れる? 他は作れないんだけど」というご相談から始まった企業なので、難易度の高い要求をいただけるのは技術側としてもやりがいを感じます。
- 田嶋氏
- 私も技術側の人間だから同感です。「無理です」って言いたくないんですよね。要求を何とかクリアして、宇宙に還元する方向に持っていこうっていうマインドになるので。御社の方々も同じマインドで応えてくださる方々だったので感謝です。
FUTURE│episode 3
高い成功率を誇る
日本のロケット事業。
先進の技術で
衛星ユーザーの信頼をつかむ。

- 田嶋氏
- H3ロケットの本格的な打ち上げが始まるのが2025年度。成功率が安定すると、相乗りで様々な衛星を乗せるのも可能になると思います。今後の日本のロケット事業に民間ロケットの存在は欠かせませんし、JAXAがひとつの参考になれたらと思います。
- 大場
- 海外にも視察に行かれるそうですが、除湿技術はどうですか。
- 田嶋氏
- 宇宙関連の施設や設備は国によって全くグレードが違います。壊れることを恐れず打っている国もあれば、日本のように手順を踏んで慎重に打つ国もある。日本で認められた技術であれば、世界中どこでもやっていけると思っています。じつはロケットは地球の自転を使って打てるので、できるだけ赤道直下で打つのが理想的。だから亜熱帯で打つケースが多いんです。デシカント除湿機のニーズは高いと思いますよ。
- 大場
- 嬉しい情報です。弊社のデシカント除湿ユニットやソリューションは世界30国以上で使用されています。海外のロケット事業にうちの除湿技術が貢献できる機会を、ぜひ探っていきたいですね。
- 藤元
- 宇宙ステーションの空調や月面基地の空調も視野に入れて挑戦したいです。
- 田嶋氏
- 夢がありますよね。私も月居住プロジェクトは様々な分野でチャレンジしています。空調の話は宇宙でも大きな課題です。深掘りしたら、いずれそのフェーズにチャレンジできるかもしれません。若い技術者にも挑戦する姿勢を忘れないでほしいですね。
- 大場
- そうですね。個人的にはうちの除湿機や除湿技術が、普通とはまた違う使われ方で様々なプロジェクトに参画できたらと考えています。除湿技術の新しい市場を拓いていきたいですね。どんどんアイデア出していきましょう!
- 藤元
- 利益の追求も大事ですが、話題性も大切。技術者として従来の製品とは一線を画す製品づくりを常に目指したいし、そこに向けて若いリソースも突っ込んでいきたいですね。田嶋さんもおっしゃったように、人生はチャレンジですから!